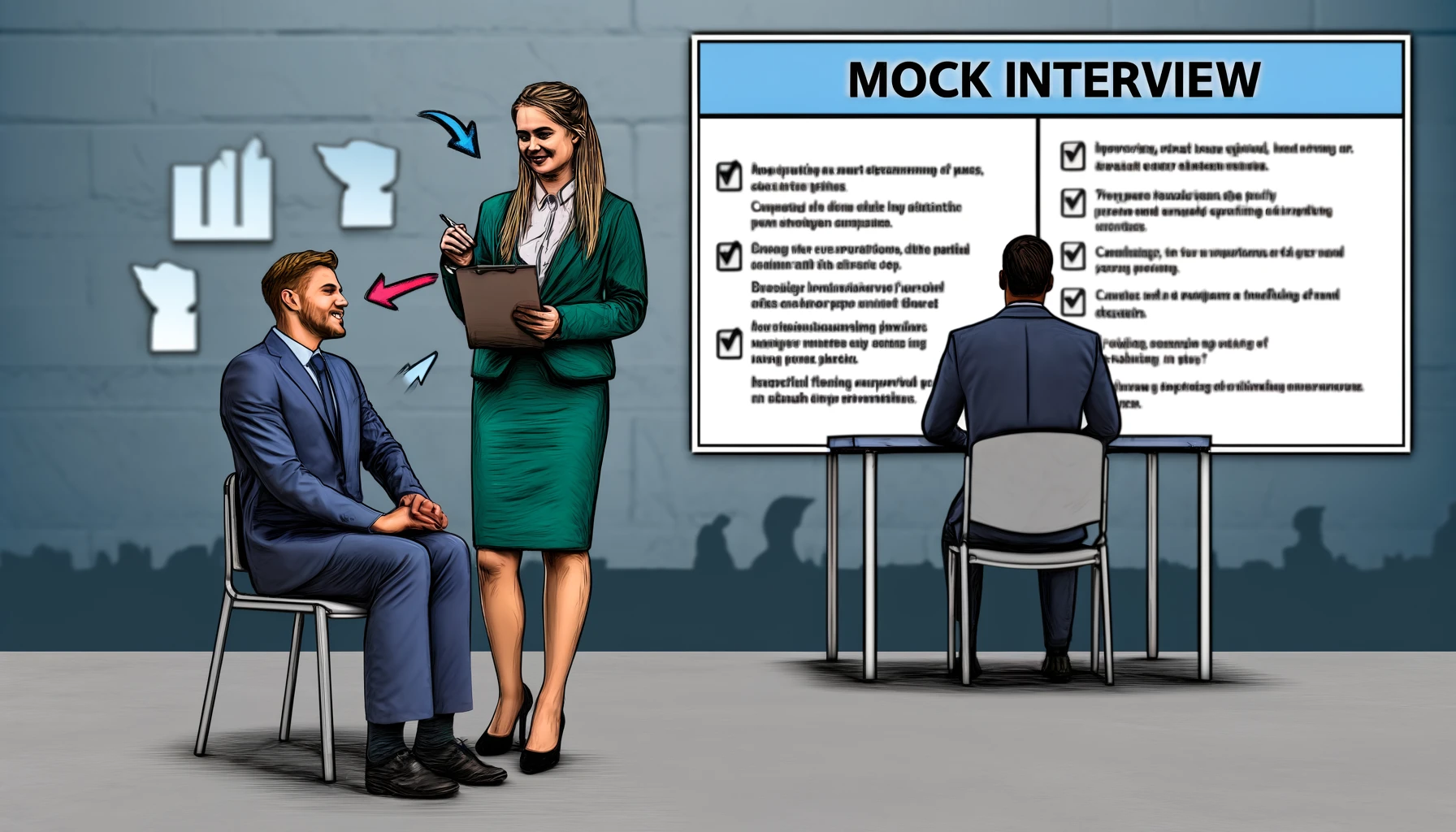面接で「ストレス解消法」を聞かれたら?|質問の意図と答え方のポイント、好印象な回答例まで解説
はじめに
面接では「志望動機」や「自己PR」といった定番の質問に加えて、少し変化球ともいえる「ストレス解消法」について尋ねられることがあります。
「面接でストレス解消法なんて、なぜ聞かれるの?」
「正直に答えていいの?」
「どんな答え方をすれば好印象につながるの?」
このように戸惑う方も多いかもしれません。しかし、「面接 ストレス解消法」という質問は、企業や学校側が応募者の自己管理能力やメンタルの安定性、考え方を知るために行う、とても意味のある質問なのです。
この記事では、
- 面接でストレス解消法を聞かれる理由
- 質問の意図と評価されるポイント
- 好印象を与える答え方のコツ
- 実際に使えるストレス解消法の例と回答例文
- NGな答えとその理由
を詳しく解説します。
なぜ面接で「ストレス解消法」を聞かれるのか?
面接官が「ストレスを感じたとき、どのように対処していますか?」「あなたのストレス解消法を教えてください」といった質問をするのは、以下のような理由があります。
✅ 面接官の意図
| チェック項目 | 見ている内容 |
|---|---|
| 自己理解力 | 自分の感情を把握し、言語化できるか |
| メンタルケア能力 | ストレスと向き合う習慣や工夫があるか |
| 長期的な適応力 | ストレスを溜め込みすぎず、継続的に働けるか |
| 社風との相性 | ストレスへの向き合い方が企業文化と合っているか |
つまりこの質問では、**あなたが「健康的に社会生活を送れるかどうか」**を見られているのです。
面接でストレス解消法を答えるときの3つのポイント
✅ 1. ポジティブで健全な方法を選ぶ
飲酒・ギャンブル・ゲーム漬けといった極端な解消法は避け、**「健康的・前向き・社会性のある方法」**を伝えましょう。
✅ 2. 実体験をもとに具体的に話す
たとえば「読書」と答える場合も、「どんな本を読むか」「どう気持ちが整理できるか」を添えることで、説得力がアップします。
✅ 3. 仕事や学業への意欲につなげる
「この方法でリフレッシュできるから、切り替えてまた頑張れる」といった、前向きな姿勢で締めくくることが好印象のカギです。
好印象を与えるストレス解消法の例と回答例文
■ 読書
私のストレス解消法は読書です。特にエッセイや自己啓発本を読むことで、自分の考えを整理したり、新たな視点を得ることができます。気持ちが落ち着くことで、冷静に物事に向き合えるようになり、前向きに切り替えることができています。
■ 運動(ジョギング・散歩・筋トレ)
ストレスを感じたときは、軽くジョギングをしています。体を動かすと頭がすっきりし、前向きな気持ちになれるため、以前から習慣にしています。リフレッシュすることで、次の日も集中して取り組むことができています。
■ 音楽を聴く・楽器演奏
私のストレス解消法は音楽を聴くことです。特にクラシックやジャズなどリラックスできるジャンルを聴くことで、自然と気持ちが落ち着きます。心を整える時間を作ることで、気持ちをリセットし、再び目標に向けて集中することができます。
■ 家族や友人との会話
ストレスを感じたときは、家族や友人と会話することで気持ちを切り替えています。誰かに話を聞いてもらうだけで、心が軽くなり、自分の考えを客観的に整理できます。コミュニケーションの大切さを実感する瞬間でもあります。
■ 料理・掃除などの生活習慣
私のストレス解消法は料理をすることです。材料を切ったり、火加減に集中したりすることで、自然と気持ちが切り替わります。完成した料理を食べて満足感を得ることで、また新たな気持ちで物事に取り組むことができます。
NGな回答とその理由
| NG回答 | 理由 |
|---|---|
| 「お酒を飲んで忘れます」 | 面接では不健康・依存的な印象に |
| 「特にありません」 | ストレス対処力がないと判断される可能性 |
| 「ゲームで朝まで起きてます」 | 不規則な生活・自己管理力の欠如を疑われる |
| 「怒鳴って発散します」 | 協調性や感情コントロールに不安を抱かせる |
→ 面接では、日常的で健康的な方法を前向きに語るのが基本です。
まとめ|「ストレス解消法」は自己管理力と人柄を伝えるチャンス
面接で「あなたのストレス解消法を教えてください」と聞かれたとき、ただの雑談ではなく、あなたの自己理解力や適応力、価値観を見られていることを忘れてはいけません。
✅ おさらいポイント:
- ストレス解消法は「健康的・前向き・継続できる」ものを選ぶ
- ただの趣味紹介ではなく、「どうリセットできているか」を明確に伝える
- できれば仕事や学業へのプラスの影響も添える
- NG回答(飲酒、暴力的な発散法、答えない)は避ける
この質問にしっかりと答えられれば、自分を客観視できており、感情管理もできる社会人・学生として信頼されやすくなります。
事前に自分のストレスとの向き合い方を振り返り、あなたらしい言葉で伝えられるよう準備しておきましょう。